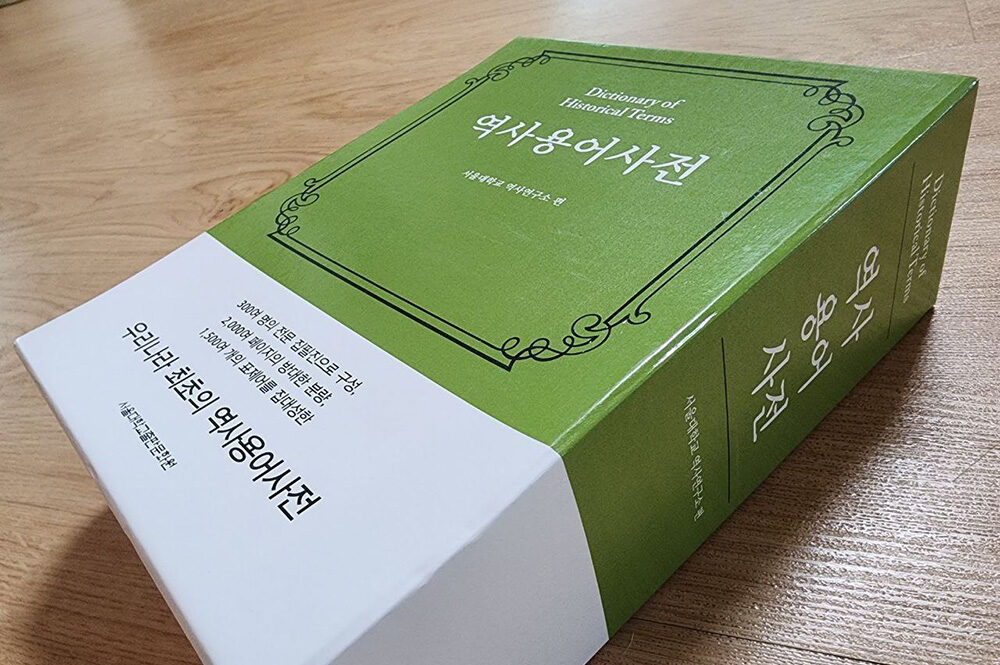歴史に対する温かな視線
良い本にどう巡り会うのか。経験上もっとも可能性が高いのは本屋に陣取り、興味をそそられる本を手当たり次第に開いては冒頭部分を読んでみることだ。時間が許すならばこの方法で100パーセントの満足度が得られる。
他方、良い本の定義は簡単ではない。人それぞれ趣向が異なるからだ。それでも敢えて挙げると「今の欲望を満たしてくれる本」「ちょうど知りたかったことを教えてくれる本」「今まで知らなかった世界や感情を経験させてくれる本」とでも定義できるかもしれない。
この定義に従う場合、本書『朝鮮が出会ったアインシュタイン』こそは誠に良い本であった。もっとも、その存在を知ったのは知人のSNSだった。なんのこっちゃ、という話であるが仕事や家事、子どもの世話に愛犬の散歩と忙しい私には、本屋で長時間本を選ぶなどという贅沢は許されていない。
新聞の書評も購読紙以外は見ることもないため、たまにSNS上に流れてくる本の紹介に釘付けになる。特に信頼できる「書籍眼」を持つ人物の投稿ならなおさらだ。本の内容を楽しげに一通り紹介したその投稿の最後には「もっと、もっと知らなければならない!」とあった。知りたい欲望を刺激する本とは最高ではないか。

本書は国を奪われた朝鮮の知識人と科学との結びつきを、1895年から1953年までという朝鮮半島の今を形作った時代を背景に、俯瞰的な視点から書き綴った一種の群像劇だ。
この間、朝鮮は大韓帝国となり、さらには日本による植民地となった。そして植民地からの解放後に米ソにより南北に分断され、1948年に成立した二つの政府が戦いを繰り広げつつ今に至るのだが、思い通りにならない歴史を前に懸命に生きた当代の知識人たちの姿が胸を打つ。
植民地朝鮮の知識人は、国を持たないユダヤ人の境遇に己を重ねたという。とりわけ、ヘブライ大学の設立に尽力したアインシュタインの存在は特別だった。
科学に造詣がある知識人たちは新聞を通じ相対性理論をいち早く朝鮮社会に紹介するかたわら、1922年に『改造』社の招請により日本を訪問したアインシュタインの動静を伝え、翌年には朝鮮各地で住民を対象に巡回講演まで開いた。
科学力が足りずに国を奪われたという認識がある中で、相対性理論を人々に知らせることは一種の独立運動でもあった。講演会場では社会主義者による住民への演説もあり、(朝鮮総督府の)警察と衝突した記録も言及されている。
他方、本書の中で1937年のものと紹介されている一枚の写真がある。
ビナロン(ビニロン)研究で有名な李升基(リ・スンギ)、朝鮮人で初めて化学を専攻した理学博士・李泰圭(イ・テギュ)、そして種の交雑研究で名高い禹長春(ウ・ジャンチュン)の3人が映っているものだ。いずれも日本で博士号を取得した彼らだが、後に李升基は北朝鮮へ、李泰圭は米国へ、禹長春は韓国へと渡り科学を突き詰めていく。著者は彼らの姿を通じ朝鮮半島の現代史を鮮やかに浮き彫りにする。
数十人に及ぶ本書の登場人物の中で、著者が最も重きを置いた人物が黄鎮南(ファン・ジンナム)だ。現在の北朝鮮、咸鏡南道で1897年に生まれた同氏は米国で学ぶ中で独立運動に関わり、その後ドイツで学業を続ける中でアインシュタインに学び、その理論を朝鮮社会に紹介した。1945年の解放後は呂運亨(ヨ・ウニョン)と共に左右合作運動を行うも、1970年に沖縄で一人さみしくその生を閉じた。
なぜ沖縄なのかはここでは明かさないが、本書から強く感じるもう一つのテーマは、日本と朝鮮知識人の関連性だ。朝鮮知識人は日本に学び、そして日本からの独立を目指した。
この複雑なアイデンティティについて、著者の閔泰基(ミン・テギ)は歴史に対する温かい視線という土台の上に、多様な資料や人物間の関係を構築することで、善悪という価値判断を排したありのままの姿として表現することに成功した。
自身も博士号を持つ科学者である閔泰基は、前作『パンタ・レイ(未邦訳)』でもその博覧強記ぶりを見せつけたが、本書により縦横無尽風とも評すべき作風を確立したと言えるだろう。
私はこの本に惚れ込み、閔泰基氏のブックコンサートにも参加してみた。楽しそうに話をする著者の姿からは心底、歴史と知識に対する敬意を感じたものだった。私の手でぜひ翻訳したい一冊といえる。