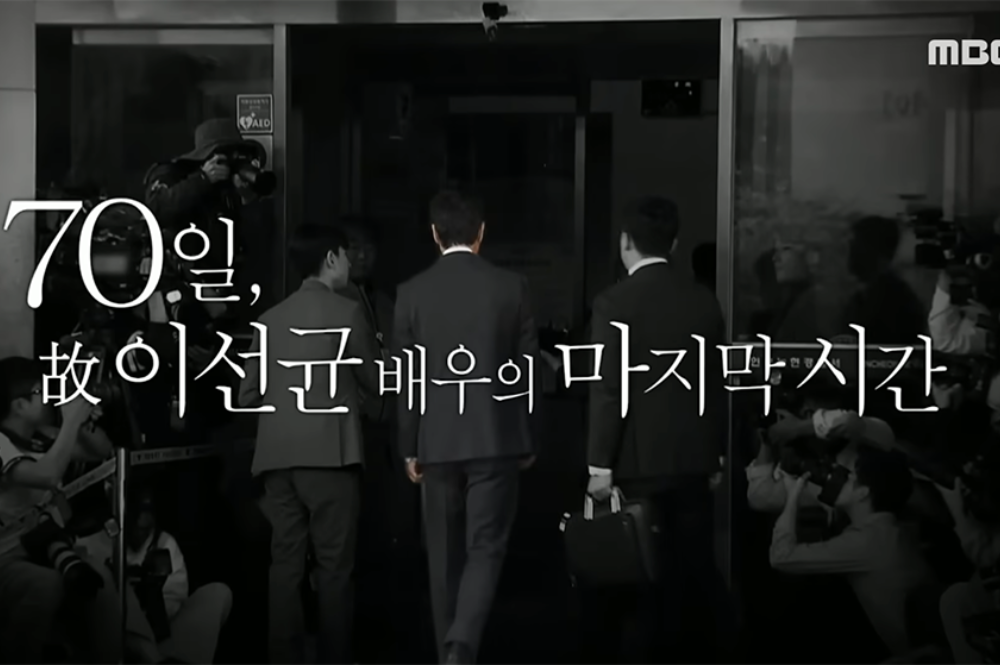ルクセンブルクに移住して15年になる姉が、健康診断のため韓国にやってきた。久しぶりの再会に喜ぶ母と家族と共にソウル市内のインド料理屋で舌鼓を打ち、近所の教保(キョボ)文庫に向かった。現地で韓国料理屋を営む姉はレシピ本をじっくり見たいという。ビルの地下一階を丸々使った韓国最大の本屋だけに日曜の夜でも活気がある。特に一枚板のテーブルで20人以上が本を読んでいる一帯には知的な熱気が漂っている。私が韓国の大学生だった20数年前にも、同じ場所でたくさんの市民が床に座り、むさぼるように本を読んでいた。韓国っていいなと思いながら私もその一団に加わったものだ。
さらに進むと一角に新設されたアートスペースで韓国の近現代美術展が開かれていた。「6人の巨匠の作品を集めた」と書いてある。居並ぶ作品の印象は正直あまり覚えていない。それよりも私の目は隅にあった参考図書の表紙に釘付けになっていた。『どこで何になってまた会うだろうか』。韓国語では어디서 무엇이 되어 다시 만나랴となる。すぐに涙が出そうになった。2年前に長い闘病のすえ亡くなった父と、昨年末に急死した父と同年代の作家の徐京植さんを思い出したためだ。ここで泣いてはまずい。「おい、こっちに来てみろ。この文章かっこよくないか」。少し離れた所にいた息子に声をかけ気を取り直した。改めて表紙を見ると、青字のタイトルの下で気難しそうだが凜々しい男性が腕組みしている。キム・ファンギのエッセイとあった。もう少し見ようとしたところで姉がやってきて時間切れとなった。

姉をホテルに送り家に戻ると夜の11時近かった。狭い仕事部屋に座り、キム・ファンギと検索してみる。韓国語版ウィキペディアの「韓国の抽象美術の先駆者であり、20世紀の韓国美術を代表する画家」という一文に続き、「キム・ファンギの『宇宙』132億ウォンで落札」という記事のタイトルが目に入ってきた。そう。私が知らないだけで金煥基(キム・ファンギ)は韓国でとてもとても有名な画家であった。
日本による植民地支配下の1913年に全羅南道(チョルラナムド)新安(シナン)郡で生まれ、33年に東京大学美術部に入学。藤田嗣治や東郷青児に指導を受け37年に帰国。韓国政府樹立後の48年から50年までソウル大学美術科教授を務め、その後も教壇に立ちながら制作活動を続けたとある。後にパリ(56年~59年)、ふたたび韓国を経て63年にニューヨークに渡り同地で74年に生を閉じた。その作風も多彩だった。「自然との一体から観照を経て超越に至る崇高の美学を、造形的に完成させていく芸術の旅程であった」という評の通り、50年代、60年代、70年代と抽象画の中で表現方法を変えていったという。
そしてひとしきり説明を読む中で再び『どこで何になってまた会うだろうか』という一文が出てきた。金煥基が60年代後半から続けてきた「点画」のうちで最高の傑作とされる連作のタイトルだった。濃い青の濃淡で描かれた点と四角がキャンバス一面を覆った作品からは画面越しでも深みのある世界観が伝わってきた。なによりも圧倒的に美しかった。私は一気に引き込まれていった。
水曜日は午前中から首都圏に大粒で湿った雪が降り注いだ。勢いはやまず、住まいのある金浦(キムポ)から約一時間かけてソウル付岩洞(プアムドン)に着く頃には道路はすっかり白く覆われていた。目的の『煥基美術館』は大通りから古い家並みが並ぶ急な丘を登った所にあった。検索の末に金煥基の絵画、中でもニューヨーク時代の点画を常設している美術館の存在を知り訪ねていったのだった。毎日ゴロゴロと冬休みを満喫している子どもたちも私の熱気にあてられたのか、素直についてきてくれた。

韓国に金珖燮(キム・グァンソプ)という詩人がいる。金煥基よりも9歳年上の1904年生まれ。高校の教科書にその詩が掲載されるほどの評価を受ける、独立運動家でもあった同氏の作品に「夕べに」という詩がある。訳してみる。
夕べに(金珖燮)訳:徐台教
あんなにたくさんの星の中から
星ひとつが私を見おろす
こんなにたくさんの人の中から
その星ひとつを見あげる夜が深まるほど
星は明かりの中に消えさり
私は闇の中へと消えてゆくこんなに情が通う
君ひとつ私ひとつは
どこで何になって
また会うだろうか
金煥基の名画の陰に金珖燮の存在があった。少し調べると画家と詩人は旧知の仲であるばかりか、ソウルの同じ地域に住んでいた。画家は詩人を敬愛してやまなかったという。しかし1970年のある日、金煥基は金珖燮が脳卒中で倒れ世を去ったと聞く。ちょうどこの時に韓国のある新聞社が始めた韓国美術大賞への出典を求められた。この時の心情を金煥基は日記にこう綴っている。「(前略)出典することを決める。怡山(金珖燮の号)の詩『夕べに』を常に心の中でうたっている。詩画の大作を作り韓国展に送ろうと考えている」。こうして誕生したのが『どこで何になってまた会うだろうか』だった。同作は大賞を受賞し、いくつかの連作が作られた。『煥基美術館』にあるものはその中の一つだ。
私は恥ずかしながら、つい数日前までこんな作品の背景はおろか金煥基も金珖燮も全く知らなかった。しかし教保文庫で見た表紙の一文から受けた印象が間違ってなかったことを知り鳥肌が立った。金煥基はキャンバスに敬愛する人物への想いをぶつけたのだ。それは父と、作家との別れを惜しむ私の気持ちそのものであった。付言すると韓国語の만나랴は様々に解釈できる。「会おうか」でもよいし「会えるだろうか」でもよい。広大な宇宙の中で出会い、そして別れるが、いつかまた会うときがくる。だから私は「会うだろうか」とした。
いつか訪れる家族や友人との別れの際にもまた、この一文を思い浮かべるかもしれない。しかし2024年のいま、私の、いや、私たちの耳には世界中で起きる悲劇と無念の死の知らせが絶え間なく届いている。金煥基の大作『どこで何になってまた会うだろうか』はそんな時代へのレクイエムであると同時に、再生への希望にもなり得まいか。否、そう考えないと精神が保たない気がする。死を希釈するつもりはないが、拠って立つものも欲しい。一つの詩句との出会いが人生を左右することがある。そんな得がたい経験をした数日間だった。
なお、後聞によると金珖燮は亡くなっておらず金煥基がニューヨークで斃れた3年後の77年に世を去った。二人がどこかで何かになってまた会っていると想像するのは私だけではないだろう。






![[映画評] 『オン・ザ・ロード 〜不屈の男、金大中〜』 今かがやく妥協と寛容の精神](https://thekoreafocus.com/wp-content/uploads/2024/11/250908_7.png)